両利き経営を実現する コーポレート・ トランスフォーメーション
日本版コーポレートガバナンス・コードが制定されてから今年でまる5年が経過する。全上場銘柄のうち、コード制定前に社外取締役を導入していた企業は3分の2程度だったが、直近ではほぼ全銘柄が社外取締役を導入している。ROEについては、足元でマクロ環境が厳しいこともあり、改善ペースは遅いものの、それでも直近期でROEが8%以上であった銘柄は全体の半数を超えている。
新型コロナウイルスによるパンデミック(世界的大流行)は、社会的、経済的にも今まであった色々なものを破壊しつつある。せっかく感染死者数を低い数字に抑え込むことに成功しても、感染流行からの回復期において経済的なリカバリーに手間取ると困窮に起因した多くの人生の悲劇を招く危険性があり、さらには深刻な経済不振が政治的な不安定やポピュリズム、戦争の誘惑を生むことも人類史の教訓である。
すなわちコロナショックからの真の復興は、経済の持続的な復興を成し遂げてはじめて成るのである。
「日本的経営」モデルからの決別
そのためにわが国においては、日本企業自身が旧来のモデルと決別し、新しいモデルを作り直す必要がある。1960年頃からの高度成長とともに形成・確立された「日本的経営」モデルで日本がピークを迎えてからのこの30年、グローバル化が進みプレーヤーが増えるという大きな環境変化に加え、デジタル革命の進展により破壊的な変化が起きた。このような環境下で、改良・改善を旨とした同質的、連続的な日本の会社――裏返して言えば事業と組織の何割かを短い時間で入れ替えるような不連続で大きな方向転換が苦手な「日本的経営」モデルは完全に行き詰ってしまった。その長期停滞のところへ感染症が襲いかかり、しかもその衝撃でデジタル革命は加速する気配である。
両利き経営へのトランスフォーメーション
破壊的イノベーションの時代を経営するには、既存事業を「深化」して収益力・競争力をより強固にする経営と、イノベーションによる新たな成長機会を「探索」しビジネスとしてものにしていく経営を両立させる「両利きの経営」が求められる。
私が早稲田大学大学院 経営管理科の入山章栄教授とともに日本に紹介した『両利きの経営』(チャールズ・オライリー、マイケル・タッシュマン共著)に登場する多数の事例研究から浮かび上がってくることは、日米を問わず両利きの経営、多元的な経営を持続的に実践するために必要な両利きの組織能力を企業が身につけることは容易ではないが、これまた日米を問わず、その成否は経営次第・経営者次第という示唆である。
デジタル革命の新しいフェーズ、すなわち自動運転や遠隔医療などのリアル×シリアスフェーズは、ハードウェアやオペレーションに強い会社にとって脅威であると同時に大きなチャンスをもたらす時代でもある。これをチャンスにできるかどうかは、両利きの組織能力を身につけるコーポレート・トランスフォーメーション(CX)が出来るかどうかにかかっている。
CXは憲法改正くらいのマグニチュード
今、求められているCXは企業の最も根幹的な部分の改革であり、憲法改正くらいのスケール、時間軸、マグニチュードの大変革にならざるを得ない。組織能力の変革度合いを表すものとして、古い日本的経営の統治機構を表す旧憲法と、それと対極にある新憲法試案との概要をまとめたものが図である。
皆さんの会社は旧憲法と新憲法の間のどのあたりにいるだろうか?置かれた状況による差こそあれ、目指すべきCXゴールは現在よりは新憲法寄りのところになる。
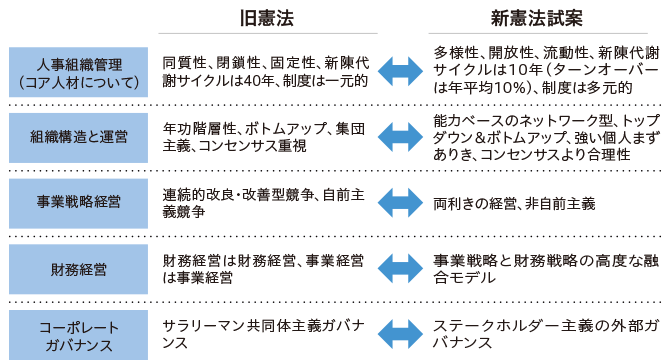
CXは一日にしてならず
新旧憲法のギャップで分かる通り、CXは極めて本質的で、長期間にわたりストレスを強いる難しい継続的な改革である。
CXを実現していくためには、まずは長期のゴールを設定することが必要である。10年後くらいの会社のカタチを新憲法のイメージにどこまで近づけるか。現在の事業ドメインと組織能力の今と10年後をイメージしながら、抽象論ではなく、各項目について具体的なKPIを置いてゴールを設定する。ここで描かれたものこそがCXゴールであり、このギャップをどの時間軸でどう埋めるかがCX基本計画となる。
経験則的に言うと、CXモードにするために一番効くのはやはり社長人事である。多くの人々が改革疲れとなり、「次はさすがに穏健派の社長だろう」と思い始めたころに前任者以上に破壊王なトップが就任すると、さすがに人々の中の抵抗する心は折れ、CXの流れに乗って自分も変容しようと考え始めるのだ。ローマにおいて共和制を破壊した革命家カエサルが暗殺されたあと、後継者になったのはさらに老獪な革命家アウグストゥスであり、彼の代で共和制から帝政へのトランスフォーメーションは完了する。CXは一日にしてならず、である。
そしてもう一点、破壊的変化が次々と起こる現代においては、10年後のCXゴール自体がムービングターゲットとならざるを得ない点も重要だ。少なくとも2〜3年に一回は、当初のゴール設定でいいのかレビューし、必要に応じて改定する必要がある。
つまり、CXの真のゴールは恒久的にCXを続ける力、持続的な企業組織の変容力を獲得することにあり、変化に対応する組織能力を持つ企業が両利き経営の時代の勝者になっていくのである。
勝負は5〜10年で決まる
デジタル革命の最終フェーズとも言うべき、リアル×シリアスフェーズにおける可能性の扉が開く瞬間が目の前に来ている。この扉が開いているのは、この先5年から長くて10年だろう。この時間軸の中で、日本企業自身が過去の成功の呪縛をいよいよ断ち切り、異次元のCX力、変容力を獲得するための会社の大改造に始動、成功することを切望している。なお、本稿の「CX革命」の方法論については、拙著『コーポレート・トランスフォーメーション』(文藝春秋刊)に詳述したので、関心のある方は参考にして頂ければ幸いである。
各界を代表する論客が企業統治について語ります。

冨山和彦Kazuhiko Toyama
株式会社 経営共創基盤 代表取締役CEO
ボストンコンサルティンググループ、コーポレイトディレクション代表取締役を経て、2003年に産業再生機構設立時に参画しCOOに就任。解散後、IGPIを設立。パナソニック社外取締役。経済同友会政策審議会委員長。財務省財政制度など審議会委員、内閣府税制調査会特別委員、金融庁スチュワードシップ・コードおよびコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議委員など要職多数。近著に、『コーポレート・トランスフォーメーション』『コロナショック・サバイバル』『AI経営で会社は甦る』『なぜローカル経済から日本は甦るのか』、他。
これまでの記事[ OPINION ]
- 略語「超」解説:DCF法(ディスカウント・ キャッシュフロー法)
- 経済界の平和への貢献とESGP
- 第三者委員会の有用性と限界を考える
- 消費減税に逃げ込む政治の危うさ
- 独立社外役員から成る調査委員会の妥当性
- AI時代の企業価値向上に向けて~トランスコスモスの挑戦
- ICGN 30th Anniversary Conference Asia: An exciting time for Corporate Governance in Japan
- 略語「超」解説:DDM (配当割引モデル)
- 親会社の社外取締役の役割と責任
- Corporate Governance Needs to Start with "Why"
- 日本の株式市場の変革をもたらす「三点セット」
- 吹き荒れるトランプ旋風
- コーポレートガバナンス改革の「実践」に向けて
- トランプ2.0、日本への余波
- 略語「超」解説:WACC(加重平均資本コスト)
- 社外取締役はガバナンス粉飾に加担するな
- 労働市場改革が宙に浮く懸念
- 人的資本経営におけるジョブ型雇用
- 味の素グループ 企業価値向上の処方箋
- 略語「超」解説:ROIC(投下資本利益率)
- 不祥事企業の社外取締役
- 株式市場で広がる「同意なき買収」
- 何が日本的経営を腐食させたか
- トップマネジメントとして備えたい「伝える力」
- 株主・投資者の目線を踏まえた経営の実現に向けて
- Purposeを起点とした価値創造とコーポレートガバナンス
- 略語「超」解説:PBR(株価純資産倍率)
- 社外取締役の説明責任
- 政策保有株の売却が加速
- 人的資本経営ブームの本当の捉え方
- 地政学リスクの時代の企業価値向上
- ACGA's market rankings for corporate governance
- 人材育成を経営戦略に生かせ
- コーポレートガバナンスの真意の共有
- 不祥事対応のリスクマネジメント~第三者委員会・調査委員会とガバナンス
- 社外取締役のトレーニングと買収行動指針
- 資産運用立国
- 指名委員会こそ、健全なガバナンス構築の根幹
- 政府が女性役員の登用で数値目標
- 人的資本経営における「安心」と確定拠出年金(DC)
- コーポレートガバナンス改革の実質化に向けて
- 事業を通じて世の中の課題解決に貢献する
- 我が国のベンチャー・エコシステムの高度化に向けた提言
- 企業価値向上とESG投資
- 不毛な「守り」と「攻め」のガバナンス議論
- サステナビリティ経営に資するコーポレートガバナンス
- グローバル投資家の視点から見た日本のコーポレートガバナンス改革
- 気候変動への取組みは待ったなし~世界の最新動向
- 「金融と 財政の悪循環」を断ち切れ
- ガバナンス議論の神髄をなすアカウンタビリティー
- CGSガイドラインの改訂で議論された方向性について
- コーポレートガバナンスとパッシブ運用
- コロナ特例 「ゼロゼロ融資」が終了
- 義務教育DXとガバナンス
- ガバナンス議論の原点を振り返る
- コーポレートガバナンス改革の点検と非財務情報開示の充実について
- 日本も財政検証機関の設立を
- 企業理念(hhc理念)とコーポレートガバナンス
- モニタリング・モデルを採用する会社における監査委員会等の監査について
- 事業法人は公益法人と協働を
- コロナ禍があぶり出した課題
- 東京証券取引所の 市場再編
- リナ・カーンの戦い
- 今後のコーポレートガバナンス改革の取組みについて
- 持続性が問われる「資本主義」
- コーポレートガバナンスを担保するのは経営者の高い志と倫理観
- 日本の製造業の展望と課題
- 危機管理としての 財政健全化
- 新市場区分と改訂コーポレートガバナンス・コードの下での企業価値向上
- コーポレートガバナンスを考えることは、経営の基本
- デジタル化と規制改革
- 社外取締役の 獲得競争が激化
- なぜ「コーポレートガバナンス」なのか
- 新型コロナウイルスと 日本における 株主アクティビズム
- 新政権の突破力が問われる労働規制改革
- 企業不祥事と 「タコツボ」
- いま求められるコーポレートガバナンスの深化
- 日立の取締役会改革
- 行政のデジタル化を規制改革の起爆剤に
- 「良き資本主義」を実現する ボトムライン革命
- 両利き経営を実現する コーポレート・ トランスフォーメーション
- 証券取引等監視委員会の活動方針
- コーポレートガバナンスの深化と市場の評価
- 次期会社法改正に向けての課題
- コーポレートガバナンス改革の今後の動向
- 新型肺炎が突きつける日本型システムの脆弱性
- 変容する米企業の株主第一主義
- 老後2000万円問題の本質
- 外為法改正の外資規制企業統治改革に逆行も
- Do the right thing ~形式と実質~
- 緊張感に包まれた歴史的な株主総会